この記事は映画を鑑賞した方を対象としています。未鑑賞の方にとってはネタバレとなる内容もありますので、ご注意ください。
本編において、映画のあらすじ紹介や、登場人物の俳優の写真等の掲載はしていません。別の同映画に関するサイトを参照してください。
人間の定義、そして現実

ノーベル賞作家となった日本生まれのイギリス人作家カズオ・イシグロの原作「Never Let Me Go(わたしを離さないで)」を映画化した作品である。原作の世界観は失わないようにはしてあるが、映画独自の脚色がかなり入った作品で題材はSF(サイエンス・フィクション)である。原作は文学性や細かい心の機微を捉えたような繊細さを感じる作品だが、映画はより「人間とは?」という哲学的な問いに重きをおいた印象を受ける。
クローンを描くことで揺れ動く人間像
映画が描く時代は過去である。すでにクローン技術が開発され、それによる医療技術の発達により人々の平均寿命が100歳を超えたという設定になっている。現実世界では、1996年イギリスでドリーという名前のクローン羊が誕生し、その後各国で次々とクローンが産まれ、2018年には中国で猿のクローンが産みだされてしまった。猿のクローンの成功、このことが意味するものは技術的には人間のクローンも確実に作り出せるということだ。
人間が人間を生み出してよいのか?それは神のみ許された領域ではないのか? すでに事態は科学の分野ではなく、倫理・哲学、そして宗教といった要素を帯びてくる。
その倫理・哲学、そして宗教という要素を取り上げて描かれたSFが、この作品である。
噴出する違和感、そして崩壊する固定概念
作品を鑑賞して、まず純粋に感じたのはSFが持つ圧倒的なパワーだった。凄まじい、映画鑑賞を進めていく中で、自分の常識や固定概念が瞬く間に壊され、まるで宇宙空間に放り出されたかのように、自分で進む方向が制御できない感覚に陥る。間違いなく漂っているのだが、どう漂っていいのか分からない不思議な感覚だ。それは、目の前で繰り広げられる状況を、一体どう受け止め、どう解釈してよいのか分からないとうことでもある。
映画は、冒頭、トミーの最後の臓器を提供するための手術が、始まるというシーンが映し出される。もちろん、この時点では鑑賞者は何が起きているのか理解はできない、映画の後半になって同シーンは再度映し出され、鑑賞者はそこで全てを理解するという仕掛けになっている。そして、シーンはほどなく主役の子供時代に切り替わり、ヘールシャムというイギリスの伝統校といった雰囲気が漂う学園生活を映し出していく。
筆者は、ここで、いきなり妙な違和感を感じさせられた。
校長を筆頭に教師全てにおいて女性しかいないのだ。これが第二次世界大戦といった戦時中であれば徴兵のため、ほとんどの男性は戦争に取られてしまっていると分からせるシーンなのかもしれないが、時代は1978年である。
また、これだけ厳格な学校でありながら、キリスト教の礼拝などのシーンはなく、キリストの像や羊といった、キリスト教のモチーフ的な物も一切登場しない。全く宗教色が排除されているのだ。

更に、学校の敷地からは一歩たりとも出てはいけないとう厳格さ、ルーシーという新任の女性教員の違和感は、そのまま鑑賞者の違和感として受け止められている。日本人には感じづらい部分があるかもしれないが、ここの教育に生徒の主体性が感じられない、一方的に教師が教え、それを厳格に守ることを強いられているのだ。これはイギリスの厳格なエリート校では逆にありえないスタイルの教育方法で、これを観たイギリス人は、とても違和感を感じたことであろう。
そうした違和感の答えを当のルーシー先生から鑑賞者は聞かされることになっていく。そして、その意味を理解した時、全校集会でタバコが見つかった事を持ち出す意味、ちょっとしたアザまで妙に気にする健康診断、野菜もちゃんと食べなさいという注意の意味、そういったものが、一気に、ただ子供の健康を気遣っているというのではなく、特別な意味を持ち出して理解されていくのである。
そして、学校の敷地から全く出ないということは、子供たちには実家もなく帰省もない。つまり親や家族がない存在なのだということを知ることにもなる。
学内にキリスト教色が無いのは、この子供達が神によって作られた存在ではなく人間が作り出した存在だからなのであろう。
ルーシー先生が意を決して語る真実、あなたたちは俳優にはなれない、アメリカに行くこともない、スーパーで働くこともない…と。
それは、まさにフランスの哲学者ジャン・ポール・サルトルが語る実存主義の内容に他ならない。人間以外のものは、産みだされた時から何になるかが決められている、目的(存在理由)が先にあって、あとから存在(実存)が作られるが、人間だけは産まれた時点では何になるか決まっていない。存在(実存)が先で、目的(存在理由)は後からくるのが人間、という考えである。
このへールシャムの生徒達は、初めから目的(存在理由)が決まった状態で産みだされてしまっている。臓器を自分のオリジナルに提供するという目的のために人間によって産みだされたクローンなのだ。
映画は、まず鑑賞者の固定概念が壊され揺らがされる状況が作り出される。そして、このサルトルの実存主義に則った人間と、そうではない人間の二種類がある世界ということを、心に刻み込まれた状態で、彼女ら主役たちの言葉や行動を受け止めていく立場に立たされるのだ。
そもそも人間の定義とは?
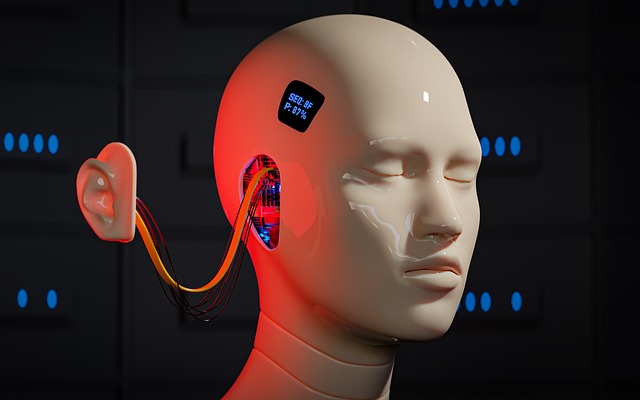
人間の飽くなき欲望が産みだしプログラム、人間までもが資本主義化されている世界、恐ろしく悲しい、そしてなんとも残酷な世界ではないか。そもそも、このクローンの技術により人間の平均寿命が100歳を超えているということになっているが、20代でほぼ死んでしまうクローン達はもちろん人間ではないという扱いで、この平均寿命の計算外なのであろう(それを計算に入れたら平均寿命ははるかに下がってしまうはず)
人間でなければ、彼女・彼たちは一体何者なのか?いや、もっと言えば、何をもって人間といえるのか? 究極とも言える哲学的な問いが襲い掛かってくる。
もちろん、現実世界ではクローン人間は倫理の問題として禁止されているが、医療技術の発達により様々な形で人間には機能を回復させる医療が成されている。実用化されているものに、義手や義足、義眼などがあるが、最近は一部の内臓なども疑似的に作れるようになってきている。人間が足や手だけを別の何かに変えても、それは間違いなく人間であるが、全身アンドロイドに脳だけ移植したものも同等に人間なのであろうか? あるいは脳の大部分を機械に置き換えられたらどうなのだろうか?どこまで自分の元々の肉体が残っていれば人間と定義されるのであろうか… そもそも、人間とはどういうものなのかという定義自体が、実はまだ成されていないのだということに気付かされる。
映画が語りかけてくる現実世界
人間の遺伝情報は両親から半分ずつ引き継ぐ、親にも、またその親があり同じ様に引き継いでいる、そしてその親もまた、その親から…遺伝情報とは自分のルーツでもあるのだ。自分の顔・姿が親に似る、あるいは似た顔立ちの多い兄弟姉妹たち、そこには、つながりを感じ自己の存在に対して自然と安心感が持てるのだという。
それに対して、この映画の主役クローンたちは、どうだろうか? 当然、親も親戚も存在しない。遺伝子のつながりといえばたった一つ、オリジナルの存在だけである。オリジナルの遺伝子を完璧にコピーした存在がクローンだ。オリジナルは人間の親子以上の深いつながりがあると言えるのではないだろうか。遺伝子のコピーは、ある意味で自分自身の分身と言える存在だからだ。もちろん、その気持ちはクローン側にだけあり、オリジナルにはないというところが残酷なのだが。
更に、それだけではないクローンはオリジナルに尽くした後、この世を去る定めにある、自分の命を捧げる存在がオリジナルなのだ。
劇中、自分のオリジナルと思われる人物を探しに行くシーンがある。なんとも複雑な思いにさせられる場面である。自分のオリジナルがクズの様な人物だったらと考えると、一体自分の存在とは何なのかと絶望感に苛まれる。しかし彼女たちには選択肢はない、桟橋のシーン、キャシーはつぶやくようにトミーに語りかける「戻らなきゃ」。
この言葉には、外泊が許されていないため、コテージに帰らなければならないという意味と、オリジナルを探す行動は止めるという意味の両方が込められた言葉としての響きを持つ。
生き方の選択も出来ず、臓器を提供するために過ごす日々。
それはサルトルの実存主義における人間の定義から外れた存在であることは先に述べたとおりであるが、ここで、もう一歩踏み込んで考えてみたい。
現実世界で、本当に人間は誰しもが生き方を選択できるのであろうか?
実は現実世界で、産まれた時から、その生き方をかなり限定されている人達は存在するのではなかろうか。
ラストに語られる主人公の叫びが心に響く
「私たちと私たちが救った人々に違いが?」
もはや、この言葉をフィクションとしてだけ受け止める気持ちにはなれない。



コメント