以下の内容は映画を鑑賞した方を対象としています。未鑑賞の方にとってはネタバレとなる内容もありますので、ご注意ください。
本編において、映画のあらすじ紹介や、登場人物の俳優の写真等の掲載はしていませんので、そういったものをお知りになりたい場合には、下記、公式ホームページを、ご参照ください。
映画『ドライブ・マイ・カー』公式サイト
ドライブ・マイ・カーのラストシーンの解釈
この映画は、いくつか衝撃的な展開を見せる箇所があるが、特にラストシーンについては謎展開となっている。観客は見終わった後、不思議な余韻にひたることになる。ここでは、その謎が残るラストシーンから進めていきたい。そこにこそ、この映画の核となる部分が描かれているようにも思えるからだ。
さて、ラストシーンの謎は以下の2点ではないだろうか?
なぜ、みさきは韓国にいるのか?
これらは映画の中で語られておらず、あくまで鑑賞者の想像に委ねられている。なぜ、こうなったのかは自由に想像して下さい、という作者の意図が見て取れるので、「こうだ」と決めつけるのは若干野暮ではあるが、個人的な想像を述べてみたい。
おそらく、ユンスが韓国での仕事の世話をしてくれたのではないだろうか?
ユンスの妻のイ・ユナが、ダンサーとして再スタートを切り、韓国に夫婦で戻ったのに併せて、みさきも韓国に移住したと考えられる。みさきは、元々ユンスに演劇でのドライバーの仕事を斡旋してもらっている。映画で、みさきが登場してから、ほぼ笑顔ゼロの彼女が、ユンス家での団らんのシーンでは、わずかだが微笑み、イ・ヨナに対してサムアップさえしている。
家福に会う前から、かなりの信頼関係が築かれていたことがわかる。特に、ユンス家の犬が異常なほど彼女に懐いていて、みさきが帰る時など、鳴いて悲しむほどということからも、何度も家に来ているということが分かる。

なぜ、家福かふくの車(SAAB900 Turbo)に乗っているのか?
それでは、なぜ韓国で、みさきは家福の車を運転しているのであろうか?
これは、家福から「譲られた」とみて、まず間違いないのではないだろう。家福が新しく何かを踏み出すために、あれだけこだわった愛車を手放したということは、「ワーニャ伯父さん」という演劇に本当の意味で向き合えた彼にとって、ある意味で必然ともいえる。妻が亡くなった後、SAAB900 Turboは単なる愛車ではなく、「音」の存在を感じれる空間、もっといえば、その存在を母に見立てて、そこにこもる胎内回帰もあったように思う。この依存状況を乗り越えた家福にとって、それは手放す必要性があったということだ。だが、愛車を譲る相手は誰でも良いわけではない、自分よりはるかに、この愛車を愛し労わることのできる、同志でもあり娘の様な存在の「みさき」に譲ることは最善の選択だったと思える。
ラストシーンに家福の姿は全く登場しない、それでいながら、彼が新たな自分となって歩んでいる姿がいきいきと想像できる、そんな秀逸なラストシーンだと思う。

みさきの左頬の傷はなぜ消えているのか?
映画の中で「手術をすれば薄くできるけど、あえて残している」とみさきが語るシーンがある。それは間接的とはいえ母親の死の原因について自らの戒めとして残している傷ということを意味している。そして、それが目立たなくなっているということは、家福が車を手放したように、みさきも母親の死の呪縛から解き放たれ、手術を行って傷を薄くし、新たな道を歩み始めた、ということを意味している。
さて、いきなりラストシーンから入ったが、前半にしか登場しない、この映画の主人公「家福」の妻である「音」について、改めて振り返っていきたい。
ドライブ・マイ・カーの登場人物たち
「音おと」と巫女(みこ)
さて、この映画は主人公の妻が亡くなるまでの前半部分がプロローグで、その2年後、仕事のため車で広島に向かうシーンからが本編という構成になっている。この映画を理解する上で最も重要なのは、主人公「家福」の妻「音」であることは言わずもがなであろう。「音(おと)」というその個性的な名前だけでなく、SEXの後に語ったことをまるで覚えていないという、巫女(シャーマン)体質が強烈な印象として鑑賞者の脳に刻み込まれる。
そして、この音(=サウンド)と巫女(シャーマン)という言葉からは、何か人間の原始的(プリミティブ)な状態を想起させられる。古代人類において巫女は神の声を伝える特別な存在であり、また銅鐸(銅製の大きな鈴)など、それまでの自然界には存在しない音というのは、人々を統べる上での特別な物であった。現代では想像し難いが、神秘的な音を作り出すということが文明の原点ともいえるのだ。この家福の妻「音」に、何か神秘性をまとわせていることが、とても印象深い。
もう少し、この「音」に踏み込んでみたい。神秘的な存在で人を魅了する彼女を、この場合ミューズと言い換えるのは、やや度が過ぎるであろうか。しかし、ただの、とめどもなく不倫を繰り返す「とんでも女子」と捉えてしまっては、この物語の世界観には入ることはできない。
改めて原作者が村上春樹だということに立ち返り、1960年代を振り返ってみると、当時はヒッピー文化の全盛期、自由や愛を掲げ、米国の若者の間で広まり、ジミ・ヘンドリックスやジャニス・ジョップリンといった当時の音楽シーンのアイコンとも言える存在を産んだ源泉でもある。
このヒッピー文化と「音」は、何か同等のものとして描かれているのではないだろうか。もちろん、この映画は別にヒッピー文化を称賛している映画ではない、あくまで、ヒッピー的な要素を持つミューズによって産み出される不思議な話が、この映画の中心に据えられているということなのだ。そう、17歳の女子高生が同級生の山賀の家に空き巣に入るという、あの摩訶不思議な話だ。
そんな音が語る話について、次に詳しく見ていきたい。

音おとの夢遊話むゆうばなし
「音」が語る話を便宜上、夢遊話(むゆうばなし)と名付けることにする。その夢遊話に登場する17歳の女子高生は「音」自身と考えて間違いないが、正確に言えば、娘を亡くしてからの「音」である。映画の冒頭でこの夢遊話が語られるのだが、それは娘を亡くしてから17年後のことであり「音」は娘を亡くした後の自分を、それまでの自分とは別人格として登場させたのだ。
ここで17歳というのは、非常に大きな意味を持つ。17歳は未成年最後の年齢である。(最近、日本でも成人年齢が18歳に引き下げられたが、アメリカなどはもともと17歳)つまり、娘を無くした未成年の私という別人格がそこに投影されているのだ。
また、同時に前世の「高貴なヤツメウナギ」は、娘を亡くす前の「音」自身だという事を意味していると思われる。そこで語られる高貴なヤツメウナギは、魚に寄生することをせず、ただ岩の上でユラユラと揺れているだけの存在、最後は餓死したのか魚に食べられたのかは分からないと語られる。解釈は映画を見た視聴者に委ねられているが、本来寄生しなければ生きていけないヤツメウナギが、寄生をしないという選択をするということは、生きることを放棄しているようなもの。それは、本来やるべきことをしなかったために娘を失うことになってしまったという自責の念の現れとも思える。
次に、夢遊話に登場する山賀という人物だが、これが家福のことであることも疑いの余地はない。若干潔癖症気味な彼の特徴は、山賀の部屋のキレイさに現されているし、鍵に対する不用心さも描かれている(彼は、鍵をかける習慣が身に付いていない)。
さて、この山賀の話は一体どういう意味を持っているのだろうか?
山賀の知らないところで空き巣に入る行為は、不倫をする「音」の背徳行為の象徴だといえる。そして、山賀が気付くように、必ず「しるし」を置いて帰るというのは、実は、その背徳行為を、夫に気付いて欲しいという、彼女の心の叫びを意味しているのだ。また、別の空き巣の登場は、彼女が高槻と自分の不倫関係を家福が知ってしまったことを示唆していると考えられる。つまり、この、もう一人の空き巣もまた家福なのだ。不倫現場を目撃した後、気付かれないように家を出ると、そのまま空港に戻る、しかし鍵をかけずに出て行ってしまったことで彼女に気づかれてしまう。空き巣との遭遇は、互いの秘密を知ったことの比喩と思われる。そして、成田空港のホテルからSkype通話で、何事もなかったかの様に振る舞う家福、モニター越しの「音」も当たり障りのない会話をして、おとぼけに合わせている。
しかしながら、彼女の心中は穏やかではなかったはずだ。強い背徳感に襲われていたはずである。そして、その気持ちが、そのまま空き巣に対する攻撃的な行為として表現されているとも考えられる。また、家福の緑内障の左目と、女子高生が最初に突き刺す左目とが一致していることも、それと分かるような仕掛けなのではないかと感じられる。何度も何度も刺すというのは、何度も何度も裏切っているということへの比喩なのであろう。
「しるし」として残したにも関わらず、最後の最後まで何も気づかないフリをする山賀に対し、ついに女子高生がカメラ越しに音声が無くても分かるように、はっきりとした口調で「私が〇した」と連呼するのだが、それは「音」がそのことを家福に伝える決心をしたことを意味している。
家福は「僕は正しく傷つくべきだったんだ」と語るシーンがあるが、その怖さから妻のある部分に蓋をしてしまった行為もまた、岩にしがみついて栄養をとらない高貴なヤツメウナギと同じといえよう。妻は亡くした子供に対して何もしなかったという自責の念にかられ、夫は亡くした妻に対して同じく自責の念にかられたのだ。

みさきの登場、そして、この映画のメッセージ
物語は、後半に向けて謎を秘めた運転手「みさき」がクローズアップされていく形で進行していく。最初は、その加速感や減速感を感じさせない運転技術と決して出しゃばらない空気の様な存在が、家福にとって居心地の良さを作り出していた。しかしながら、徐々に二人の距離は縮んでいくのである。そのきっかけとなるのがカセットテープに録音された「音」の声だ。みさきは、家福・音夫婦の亡くなった娘が生きていれば、自分と同じ23歳だということを知る。そして「音」と同じく二面性をもつ「みさきの母」の話が語られていき、「家福の妻、音」と「みさきの母」が妙な形でリンクしていく、つまりそれは心情的で疑似的ではあるが、家福とみさきが、ある意味での父子の様な様相も帯びていくのである。そしてクライマックスとも言える家福とみさきが抱き合うシーンで、この映画の強いメッセージが語られる。
『どんな人にも多面性がある、その一つの面だけを見よう(見せよう)としていないか?
その全ての面を、あるがままとして受け入れることはできないのか?』
人と人が本質的に繋がるということを、深く考えさせられる強いメッセージである。
さて、人と人との繋がりといえば、「音」をめぐって、そして役者として家福と繋がっていく、高槻について語らないわけにはいかない。それを次に語っていきたい。
高槻、そしてワーニャ伯父さん
さて、ここで理解しがたい人物、高槻について語らずに終わるわけにはいかない。高槻は難しい役回りで、ある面では単なるご都合主義的なキャラクターともいえる。つまり、彼は「家福」が妻である「音」の真実を知るきっかけを与えてくれる人物として描かれており、それ以外の部分の彼の行動、家福との関係については分かりにくい人物として映るのだ。だが、高槻は家福に夢遊話の続きを伝えるという役回りだけではない、この映画で別の重要なメッセージを持った登場人物として描かれている。
高槻を掘り下げるには、劇中劇のチェーホフ「ワーニャ伯父さん」の物語の内容を把握する必要があるが、この劇中劇のワーニャを知ることによって、家福が「音」の死後、どうしてワーニャが演じられなくなったのか、その意味を理解することができる。そして、そのことを通して高槻という存在が浮き上がってくるのだ。
ワーニャは人妻であるエレーナに恋をしてしまうという役どころ。高槻がエレーナ役の中国人女優と関係を持つというシーンが描かれているが、大事なのはそこではなく、高槻が不倫関係にあった、「音」をエレーナに見立てているというところがポイントとなるのではないだろうか。
家福からワーニャという配役を言い渡された時に、高槻がたじろぐシーンが描かれているが、なぜ高槻に年齢の合わない役柄を配役したのか? これには次の二つの意味があると考えることができる。一つは、高槻の役者としての才能を認め、自分が演じてきたワーニャを彼に任せることにした、ということである。もう一つは、不倫をしていたことを知っていた家福が、それを暗にほのめかすためにわざとその配役をした。
人妻エレーナ=「音」だと考えるのには、それなりの根拠がある。「ワーニャ伯父さん」の中でワーニャが初めてエレーナと出会ったのは、彼女がまだ未婚だった時で、「なぜあの時、求婚しなかったのか」とワーニャが後に後悔する場面があるのだが、その出会った時のエレーナの年齢が実は17歳なのである。あの「音」の17歳と完全に重ねられているのだ。これは、この映画が明らかに意図してそうしているのは間違いないであろう。
家福がなぜ「音」の死後、ワーニャを演じられなくなったのか、それはエレーナを言い寄るワーニャを拒絶するが、かといって夫を愛しているわけではないのである。映画の中の劇中劇でも描かれているが、そんなエレーナをワーニャが罵(ののし)るシーンがある。「あの女の貞淑さは、徹頭徹尾まやかしなのさ」というセリフである。その内容は「音」を思い起こさせ、家福がそれに耐えられなくなったシーンとして描かれている。
一方で、家福は高槻を認めている。何故ワーニャ役をまかせたのかを高槻に語る「君は相手に自分をさらけ出すことができる」。「音」に自分をさらけ出すことが出来なかった家福、その足らない部分を高槻は持っている。ただ、高槻はその社会性の欠如により舞台を降りることになる。
そんなた、高槻の行動に、一見救い様のなさを感じてしまうが、それにこたえるものこそが「ワーニャ伯父さん」のエンディングシーンである。映画の劇中劇でも印象的に映し出されている。「重荷を背負った人生だとしても、一生懸命生きていれば、いつか死を迎えるその時こそ、本当の安楽が得られるのだ。」というソーニャ(手話のイ・ヨナが演じている役)のシーンで幕引きとなる。このソーニャの言葉は、イ・ヨナ自身の言葉としても強いメッセージ性があるが、これは家福、みさきにも重なる、高槻のこれからの人生に対しても語られたものでもある。そして、それは誰しもが共感できる強いメッセージなのではないだろうか。

チェーホフとこの映画のつながり
劇中劇として使われるチェーホフの「ワーニャ伯父さん」。
もちろん、家福や高槻といった登場人物との相関関係は具体的に感じられる。しかしながら、この映画全体が醸し出している空気感こそが、どこかチェーホフを感じさせるのではないだろうか。
これは、たまたまこの映画の公式サイトを見ていた時に、ミュージシャンの坂本美雨さんが寄せていた映画に対するコメントで気が付いた。
静けさの果てに、人の本当の心が溢れ出す瞬間は時が止まったように美しく、思わず、息を止めていた。
引用元:映画『ドライブ・マイ・カー』公式サイト
チェーホフは、劇作家のマクシム・ゴーリキーに宛てた手紙で、次の様な言葉を残している
「人間がある明確な行動に対して、可能な限り少ない動作の数を費やすとき、それは優美である」
まさに、これがチェーホフと、この映画全体を通して流れる共通した優美性なのではないだろうか。
人と人の繋がりとは
この映画では、様々なコミュニケーションについて描かれている。言語は日本語だけでなく英語、韓国語、中国語、タガログ語、ドイツ語、マレー語、さらには韓国手話まで登場する。印象的だったのはタバコなども人間同士の距離を縮めるコミュニケーションツールとして描かれており、また車という開放的でありながらも、閉鎖された独特なプライベート空間が自分の内面に向き合い、そして人と語り合うのによい場所なのだということを改めて認識させられた。
また、あえて感情表現をしない棒読みの読み合わせ。そしてユンスが日本に来た理由が「能楽」ということも意味深い。そこには、先のチェーホフの言葉にあるような優美に繋がる世界観があるが、同時に「能楽」の数少ない表現が伝える何かというものは人間の潜在意識や深層心理、そういったものへと繋がる何かがあるのかもしれないと考えさせられた。
人が何かを伝え、そして共に認識するということを改めて深く見つめなおす、そんな作品だったのがとても印象深い。


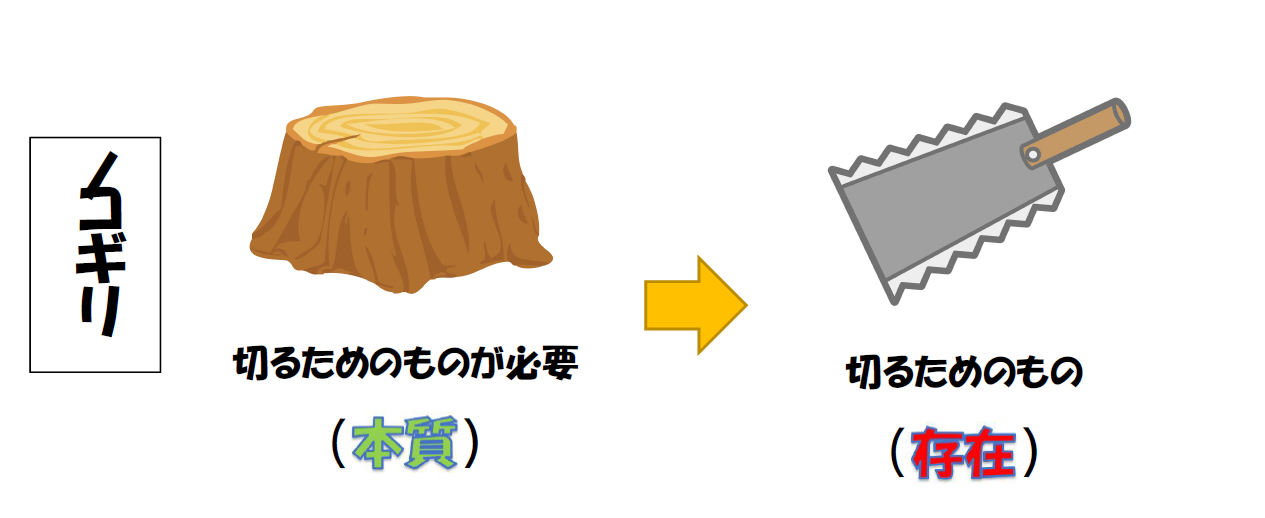

コメント