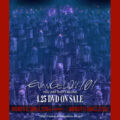この内容は完全にネタバレになります。
映画をまだ見ていないという方は注意願います。

前回は、シンジがミサトの家に同居するところまででした。![]() ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 つぶさに見てみた(4.ゼーレ会議~ミサトの家)
ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 つぶさに見てみた(4.ゼーレ会議~ミサトの家)
今回は、ミサトの家でのシーンから、学校、エヴァの訓練のシーンまでを見ていきます。
ページコンテンツ(目次)
ミサトの家での生活(夕食・風呂) そしてウォークマン
「まぁ、ちょ〜っち散らかってるけど、気にしないでね」
「(これが……ちょっち?)」
「あ、ごめん。食べ物冷蔵庫入れといて」
「あっ、はい」
「氷。ツマミ。ビールばっかし。どんな生活してんだろ」
「いっただっきま〜す!」
「いただきます」
「ぷっは〜!く〜っ!やっぱ人生、このときのために生きてるようなもんよねぇ〜!ん?食べないのぉ?けっこういけるわよ~、インスタントだけど」
「いえ、あの、こういう食事、慣れてないので・・・」
「駄目よ!好き嫌いしちゃあ!」
「いえ、ち、違うんです。あのう・・・」
「楽しいでしょ?こうして他の人と食事するの」
「は、はい」
「さて、今日からここはあなたの家なんだから、な〜んにも遠慮なんていらないのよ」
「あっ、はい」
「も〜、はいはいはいはいって辛気臭いわね〜。男の子でしょ?シャキッっとしなさいシャキッと!」
「は、はい!」
「ま、いいわ、いやなことはお風呂に入って、パーッと洗い流しちゃいなさい!風呂は命の洗濯よ」
「うわぁ〜!ミミミ、ミサトさん!」
ミサト
「何?」
シンジ
「ああ〜!あ、あ〜あ!あれ!?」
ミサト
「ああ〜彼?温泉ペンギンと言う鳥の仲間よ」
シンジ
「あんな鳥がいるんですか?!」
ミサト
「15年前はね、いっぱいいたのよ〜。名前はペンペン。縁があってうちにいる、もう一人の同居人。それより、前、隠したら?」
シンジ
「ん?うぅ!」
ミサト
「(ちと、わざとらしくはしゃぎ過ぎたかしら?見透かされてるのはこっちかもね)」
「(葛城ミサトさん、悪い人じゃないんだ)」
シンジ
「でも、風呂って嫌なこと思い出す方が多いよな」
「予備報告も無く、唐突に選出された三人目の少年。それに呼応するかの様なタイミングでの使徒襲来。併せて、強引に接収された碇司令の息子・・・確かに違和感残る案件ね。しかし、あの使徒を倒したって言うのに、あたしもあんまり嬉しくないのね」
「(ここも知らない天井か。当たり前か、この街で知ってるとこなんて、どこにも無いもんな・・・なんでここに居るんだろう」
「シンジ君、開けるわよ。一つ言い忘れてたけど、あなたは人に褒められる立派なことをしたのよ。胸を張っていいわ。おやすみ、シンジ君、頑張ってね」
シンジの大人への成長物語、ミサトの大人としての成長物語
ヱヴァンゲリヲンは、シンジの大人への成長物語として描かれています。それは、庵野秀明監督自身の投影としてのシンジが描かれているからで、だからこそリアルな14歳、リアルな中二として描かれているのだと思います。しかし、そこに、シンジの成長物語と、ほとんど並列して、シンジの成長物語のためではない、ミサトの大人としての葛藤が描かれているようにも思えます。
葛城ミサトは、NERV(ネルフ)でもハイクラス、多くの男を従えてバリバリ働く、女性キャリアの星的存在。
そこには、いわゆる1980年代には、まだまだ根強く残っていた男性が求める、社会一般通念としての「女性らしさ」のイメージがあって、それと戦うウーマンリヴの葛藤をミサトを通して描いているようにも思えます。
男女雇用機会均等法の施行で、一気に女性の地位が改善し、これ以降、どんどん女性の社会的地位が上がっていきます(今、現在に至っても世界的に見ると先進国の中では最下位クラスですが・・・)
それは単純に女性にとってハッピーなだけの事象かというと、そうでもなく、女性は女性で、従来の女性らしさとの間で葛藤していた人達が多くいたのだと思います。
そんな葛藤する女性の一人としてミサトは描かれています。
ちなみに、彼女の階級は二佐、これは、今の自衛隊の二佐を、分かりやすく警視庁に当てはめると、なんと警視クラスです。
警視クラスとえば、警部より上、ドラマ相棒でいえば「及川光博、山西淳」の役になります。
従来の、女らしさ「家事全般、特に料理や洗濯、掃除はそつなくこなす」これを捨てて、ひたすら仕事に打ち込む、仕事の出来る女性としてミサトを描いています。
そして、それまで男にだけ許されれていた、仕事をしてきた対価として夜は酒を飲んで酔う(多少酔っぱらったとしても、過酷な仕事を乗り越えているのだから、許されるという暗黙のルール)、まさに、そんな男性に成り代わっている新しいタイプの女性としてミサトは描かれていると思います。
山口の銘酒 獺祭の瓶を並べ、ビールを一気に飲んで「ぷっはぁ~」という態度は、その象徴ともいえる表現でしょう。
温泉ペンギン PEN2
温泉ペンギンのPEN2(ペンペン)、このペンギンが、この新劇場版で制作サイドが一番扱いに困った存在なのではないでしょうか?
その証拠に、新劇場版の後半には一切出てこない存在となってしまいます。
しかし、このペンギン、PEN2(ペンペン)には、実はそれなりのリアルさと意味があります。まず、ミサトの父はミサトを連れて南極へアダムの調査を行いに行き、セカンド・インパクトに遭遇してしまい命を落としてしまうという事が描かれています。
PEN2(ペンペン)は、その際か、その後、ミサトが南極に行った時に連れてきたペンギンと考えられます。
つまり、父との思い出としての存在になるわけです。
そして、実は日本でも昔、まだ捕鯨船が禁止されていなかった頃、アラスカ方面に捕鯨に出ていた船が、ペットとしてペンギンを連れてきていたという事実があります。
誤解が無いように説明をしておきますが、それはワシントン条約が締結される前の話で、ペンギンを連れて帰ることが認められていた時代の話であって、今現在は、もちろん禁止されていてペンギンを勝手に持ち帰ることなどできません。
ワシントン条約締結は1975年なので、ミサトの言う15年前というのは、その前ということになります。
PEN2 (ペンペン)は、意外にも時代の生き証人的存在だったのです。
風呂につかっている時間、そして寝る前
一日の事を振り返る時間…
恐らく多くの人は、風呂で湯舟につかっているいる時間と、眠りに入る前のベッド・布団に入った時間ではないでしょうか?
それは、単純に一日を振り返る、思い返す時間で、良いことがあれば、それを思い返すし、悪いことがあれば、それを思い返す。そんな時間なのだと思います。
つまり、シンジの言う「風呂って嫌なこと思い出す方が多いよな」というのは、別に風呂に入ること=嫌なことを思い出す時間ではなくて、単純に、シンジの今までの生活の中で、嫌な事が多い人生を歩んできたことの積み重ねで、そういう結果になってしまっている、それだけのことなのだと思います。
もちろん、それは、明らかにネガティブシンキングのシンジだからこそ、常にそいういう結果を生み出しているという事も言えます。
エヴァの話の本筋からは外れますが、心理カウンセリングには、行動療法という手法があって、行動がメンタルな部分を改善するという事があります。
もしも、お風呂や寝る前に嫌なことを思い起こしてしまうという人は、あえて、お風呂に入る時、そして寝る前に無理やりでもいいから、何か楽しいこと、奇跡に近くてもいいから起こりえるであろう良いことを想像してみることも、自分自身の状態を変えていく一つの手段だと言われています。
シンジは寝ながらウォークマンを聞いています。
もう、これは完全に寝る前の習慣・儀式になっているのでしょう。
これも、嫌な事を思い出すことを、曲を聴くことで打ち消そうとしている行動であることは間違いありません。
それにしても、決まったように25曲目でテープの片面が終わり、オートリバースが働いて26曲目がかかります。
この時点では、曲の内容は分かりませんが、これが無いとシンジは寝られない位、重要な曲となっていることが伺えます。
学校、そしてエヴァの訓練のシーン
「すまんなあ、転校生。ワシはお前を殴らないかん、殴っとかな気が済まへんのや」
「悪いね、この間の騒ぎで、アイツの妹さん怪我しちゃってさ。ま、そういうことだから」
「僕だって、乗りたくて乗ってるわけじゃないのに」
「どこが人に褒められることなんだろう。エヴァに乗ってたって言うだけで、なんで殴られるんだよ」
子供には子供の社会がある
これは、学校でのいじめの問題も含んでいる内容だと思います。
学校は、親や兄弟が入れない、完全に子供達の社会、そこでのいじめは、いくら家で大人たちが何を言おうが関係のない世界。
学校の先生も介入が出来るのかというと、それも非常に難しい子供だけの世界が存在していると言えます。
もちろん、このトウジのシンジに対する行動は、今後も、続くであろう学校での陰湿ないじめとしては描いていません。
ミサトが大人としてシンジを励ましてあげようとしても、そんなものが一瞬で崩れてしまう、子供の社会というものが学校には存在しているんだということが、よく分かるシーンだと思います。
色々と考えさせられるシーンではあります。
「いい?シンジ君」
シンジ
「はい」
リツコ
「使徒には、必ずコアと呼ばれる部位があります。その破壊が、使徒を物理的に殲滅できる唯一の手段なの。ですからそこを狙い、目標をセンターに入れてスイッチ、これを的確に処理して。感覚で覚え込んで」
シンジ
「はい」
リツコ
「結構。そのままインダクションモードの練習を続けて」
シンジ
「はい」
マヤ
「しかし、よく乗る気になってくれましたね、シンジ君」
リツコ
「人の言うことにはおとなしく従う、それがあの子の処世術じゃないの?」
シンジ
「目標をセンターに入れてスイッチ・・・目標をセンターに入れてスイッチ・・・目標をセンターに入れてスイッチ・・・目標をセンターに入れてスイッチ」
人の言う事にはおとなしく従う
人の言うことにはおとなしく従う…それは、必ずしも大人からの命令や、指示のことではなく、クラスメートや周囲がもたらす空気感のことも現しているのではないかと思います。
何か目立つことをすると、何かと問題が起こるから、当たり障りのないように周囲に合わせておとなしくしておく。
そんな行動も、人の言うことにはおとなしく従う、という中に入るのだと思います。
現在は、必要以上に場の空気を読んで、対応を決める人達にあふれている時代、特に若者達に、その傾向が進んでいると思います。
そんなことを、代弁する存在としても、シンジは描かれています。
少年・青年たち、本当にそれでいいのか?
個人的には、そんな問いかけを感じなくはいられません。
「そう言えばシンジ君、転校初日からクラスメイトに殴られたそうじゃない。パイロットのセキュリティ、大丈夫なの?」
ミサト
「諜報部の監視システムに問題はないわ。大した怪我じゃないし。それに、プライベートには極力干渉しない方がいいのよ」
リツコ
「一緒に住んでるのに?彼のメンテナンスもあなたの仕事でしょ?」
ミサト
「だからこそよ。彼、思ったよりナイーブで難しい」
リツコ
「もう泣き言?自分から引き取るって、大見得切ったんじゃない」
ミサト
「うっさいわねぇ~」
リツコ
「そうね、確かにシンジ君て、どうも友達作るには不向きな性格かもしれないわね。ヤマアラシのジレンマって、知ってる?」
ミサト
「ヤマアラシ?あの、トゲトゲの?」
リツコ
「ヤマアラシの場合、相手に自分のぬくもりを伝えたいと思っても、身を寄せれば寄せるほど身体中のトゲでお互いを傷つけてしまう。人間にも同じことが言えるわ。今のシンジ君は、心のどこかで、その痛みにおびえて臆病になっているんでしょうね」
ミサト
「ま、そのうち気付くわよ、大人になるってことは、近づいたり離れたりを繰り返して、お互いが余り傷つかずにすむ距離を見付け出すってことに」
リツコ
「そうなるといいわね……」
ミサト
「しっかし、いつになったらこのB棟の設備改修予算、下りんのかしら」
リツコ
「エヴァの維持と、清掃管理が最優先ですもの、もう無いんじゃない?」
ミサト
「足が冷えてたまんないのにね?」
大人同士の関係とは?
このシーンは、子供のつながりと大人のつながりを言い表している名場面ではないかと思っています。
「ヤマアラシのジレンマ」心理学では「ハリネズミのジレンマ」と呼ばれることもあります。
ここで、ミサトが言う「大人になるってことは、近づいたり離れたりを繰り返して、お互いが余り傷つかずにすむ距離を見付け出す」
これが、まさに子供と大人の違いを言い当てている確信的な言葉だと思います。
大人同士というのは、子供時代の友達の様に、出会ってすぐにキャッキャ言いながら仲良くなるということは出来ません。
大人である以上、多かれ少なかれヤマアラシ・ハリネズミ的に相手を突き刺す衣を着ているからです。
お互いを傷つけないように、探りながら友達や仕事仲間など、時には恋愛も含め、大人は距離を探っている存在なんだと思います。
これは、一見シンジを気にかけて言っているようにも思われますが、その実、ミサト自身も、この距離感で悩んでいるのではないかと思います。
大胆な作戦の立案、そして即時決断と実行といった仕事での人付き合いは問題ないのでしょうが、仕事を取り払った状態での人付き合いは、ちょっと苦手な様にも描かれている気がします。
引っ越したばかりとはいえ、あの部屋では人を家に呼ぶなんていうことはしていないでしょうし(笑)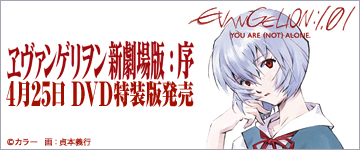
![]() 【前回】ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 つぶさに見てみた(4.ゼーレ会議~ミサトの家)
【前回】ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 つぶさに見てみた(4.ゼーレ会議~ミサトの家)
![]() 【次回】ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 よくよく見直しての気づき (6.新たな使徒~家出)
【次回】ヱヴァンゲリヲン 新劇場版 序 よくよく見直しての気づき (6.新たな使徒~家出)
スポンサーリンク